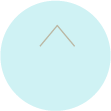【弁護士ログニュース=6月18日】江尻隆弁護士、元部下の美人アソシエート弁護士との婚約不履行損害賠償請求事件、江尻弁護士側の第一回準備書面が提出される
- 2014.6.18
- 弁護士情報

元部下の女性弁護士から損害賠償請求を受けている江尻隆弁護士
江尻隆弁護士が元部下の女性弁護士から婚約不履行で訴えられている事件で、江尻氏側から第一回準備書面が提出されましたので、以下、全文を掲載いたします。
平成26年(ワ)第9289号
原告 森順子
被告 江尻隆
準備書面(1)
平成26年6月18日
東京地方裁判所民事第30部ろA係 御中
被告訴訟代理人 弁護士 鮎沼希朱
第1 請求の原因に対する認否
1(1)訴状請求の原因第1(1)①については、原告と被告は仕事上の付き合い(金融関係の案件)で昭和63年(1988)年11月頃知り合ったこと、当時、原告は他の事務所の勤務弁護士であったこと、被告は桝田江尻法律事務所(以下、名称の変更もあるため「本件事務所」という)の経営側弁護士であったことは認め、その余は否認する。なお、当時原告が所属していたのは、友常木村見富法律事務所(旧称は小松友常法律事務所であり、当時は小松綜合法律事務所と別れて友常木村見富法律事務所になっていたが、弁護士10数人が所属していたと思われる)であり、被告が所属する本件事務所もパートナーが10名弱、アソシエートが10名弱の事務所であって、欧米型ローファームを志向するいわいる渉外事務所であった(乙1「日本のローファームの誕生と発展」参照)。
同②については、平成2(1990)年、原告がニューヨークへの留学が決まり、留学後の就職先として、本件事務所への入所を希望する旨を被告に伝え、被告が本件事務所のパートナー会議にかけた上で、原告の留学後に入所を認める旨のパートナー会議の決定結果を伝えたという限度で認める。
同③については、原告が平成3(1991)年11月に本件事務所に入所して勤務を開始したことは認めるが、その余は否認する。原告は自力で研修先を見つけられなかったので、(入所前の原告に対する好意として)本件事務所が当時懇意にしていたRoger&Wells法律事務所に打診して、短期であればという条件で原告の研修を受け入れてもらったという経緯である(注・研修先となる法律事務所は給与支払いをしなければならないので、受入れは負担となる)。
(2)同(2)については争う。ここで述べられていることは、原告及び原告代理人の極端な主観に基づく独自の見解である。
なお、少なくとも渉外事務所において、「ボス弁」「イソ弁」の呼称を用いることはなく、また司法制度改革審議会で法務省が配布した資料によれば、昭和62年~63年ころの状況として、合格者の平均年齢は28歳で、平均受験期間が6~7年であるとされているので(乙2司法制度改革審議会第8回配布資料「司法試験制度等改革の経緯」)、訴状の「合格には通常大学卒業後10年近くかかり、合格平均年齢は優に30歳を超えていた」との部分は明らかに事実に反する誇張である。
2(1)同2、1について、平成3(1991)年12月当時、原告が独身・35歳・弁護士経験4年であったこと、被告が49歳・弁護士経験22年であったことは認め、被告が原告を誘って霞が関ビルの地下の和食屋に行き、その後二次会に行ったことは特に記憶がないものの、本訴において争わず争点にしないこととし、その余は争う。
なお、被告が原告を、霞ヶ関ビルの地下の和食屋(注・料亭ではない。現在のものであるがどうビル内のレストランの傾向について乙4参照)に誘ったとすれば、同ビルは当時の本件事務所(三井商船ビル内)の道を隔てたすぐ向かいのビルであって(乙3の地図参照)、仕事帰りに寄るのに都合が良く、被告がたびたび職場の者らと利用していたものであるため、入所後まもなくの原告を思いやってコミュニケーションを図ろうとしたためと思われる(乙1「日本のローファームの誕生と発展」参照)。
(2)同2のうち、被告の行為については、原告の意に反すると述べる部分(「強引」「一方的」「突然」の語句)は否認するものの、行為の存在自体は本訴において争わず本訴の争点としないこととし、その余は争う。
なお、原告が、当時、葛飾区で両親と同居していたのであれば、被告の自宅(千葉県市川市)と方面が同じであるので、被告がタクシーで帰宅する際に原告を同乗させて原告自宅に送り届けたことは十分考えられるし、自然である。
(3)同3について、被告の行為については、原告の意に反すると述べる部分は否認するものの、行為の存在自体は本訴において争わず争点としないこととし、その余は争う、
(4)同4について、被告が結婚を申し込んだこと、(訴状の記載が曖昧であるが、仮に被告が言ったという趣旨であれば)被告が長年連れ添った妻との離婚の手続きに手間も時間もかかると言ったこと、原告が用賀駅近くに借りたマンションについて事前に被告と相談したこと、それにかかるマンション代等について被告が後で支払うと言ったことは否認し、原告の内心にかかる事実は知らず、その余は本訴において争わない。
被告は、原告に対して、妻と離婚したいとか、離婚手続きをするなどと述べたことは一度もなく、いわんや結婚を申し込んだこともなく、原告も被告に対して、被告と結婚したいなどと述べたこともなければ、原告の結婚や家庭に対する考え方を話したこともなかったのであって、そのような身上に関する事柄が原告と被告の間で話題とされたことはなかった。(被告としては、原告には恋人がいてもおかしくないと思っていたが、そのようなことが原告と被告間で話題になることもなく、原告は当時35歳以上で海外留学も経験し渉外事務所でパートナーにならんとする年代であったので、結婚のことをとりたてて話題にするような状況でもなかった。)
(5)同5については、原告と被告が結婚生活の状況であり、被告が原告に対して事務所にも家族にも隠しておいてくれと言ったとの事実は否認し、原告の内心と心身の状況は知らないが、用賀のマンションの家賃を原告自身が負担していたことを含めてその余は本訴において争わない。
なお、被告は原告と会って食事等をともにすることがあったが、被告が原告と会う頻度は、多めに見積もっても月1回程度であったと思われる。
(6)同6については、否認する。
(7)同7については、IPBA(環太平洋弁護士協会)が渉外大手の他の弁護士らが立ち上げた弁護士の国際会議であること、また、被告が平成7(1995)年から同10(1998)年まで事務総長をしていたこと(注・被告はIPBAの理事であったことはなく、また平成6年(1994)年には事務総長でもなかった)は認め、原告がシンガポール、ニュージーランドのオークランド、米国のサンフランシスコに出張したことは争わないが、その余は否認ないし争う。
原告は、本件事務所入所当時は金融分野を専門としていたが、折からのバブル崩壊とその後の景気低迷により金融関係の案件が少なくなる状態となり、業務拡大のため倒産分野に力を入れることとしたため(景気が悪くなると金融分野は下向きになり倒産分野は上向きになるなど相互保管する関係にある)、被告は、倒産分野では著名な弁護士で旧知の三宅省三弁護士に原告を紹介するなど原告に助力した。三宅省三弁護士は、原告を、東京弁護士会の倒産部会への入会を勧め、東京地方裁判所の破産部に口添えをしたほか、英語ができる国際倒産弁護士とすべく国際的倒産ネットワークに原告を入れてその存在感を高めるため、IPBAの倒産法委員会(Insolvency Committe)に原告を所属させて同委員会の運営にかかわらせ、平成9(1997)年には同委員会の副委員長に原告を推薦するなど引き立てた(乙5の1~4 三宅省三弁護士と原告とのファックスのやりとり、乙6 原告の弁護士紹介(倒産法を専門分野の一としていること))。原告は、三宅省三弁護士による原告の副委員長推薦が受け入れられた知らせを受け、「Vice Chairだあ~!」と喜びをあらわにしているが(乙5の4)、これは、この肩書きが原告に箔をつける重要なものであったことを物語る。このような経緯で、原告は、平成6(1994)年頃から、三宅省三弁護士の引き立てのもと、毎年、IPBAに参加するようになっていたものであり、原告主張のシンガポール、ニュージーランドのオークランド、米国サンフランシスコは、いずれも、IPBA(倒産法委員会)への参加を言うものと思われる。
そして、本件事務所では、パートナーは、自らの業務拡大活動にかかる経費は国際会議出張を含め自らの経費によりまかなわれることは当然であったので(本件事務所の経理制度上それが当然であった)、原告が、パートナーであった期間(平成7(1995)年以降)について、原告自らがIPBA参加費用を負担するのは、そもそも当然至極のことである。本件事務所からは、毎年、IPBAに複数のパートナー弁護士が参加していたが、いずれも自らの経緯負担によって参加している。また、平成6(1994)年については、原告はパートナーになる前年であったが、アソシエートに関しては、本件事務所が経費を負担して派遣するのは留学前の若手1人のみであったので(有望な留学前の若手に将来の外国人弁護士との付合いの訓練のために海外に行かせるといった意味合いであったため)、留学も終えてパートナー目前の原告が今後の業務活動拡大のために参加する場合に事務所による経費負担がなかったのは、これも当然のことであった(本件事務所としては、アソシエートである原告が、国際会議の間、事務所の仕事を行わないことを許容することをもって、原告の業務拡大活動に協力していた)。平成6(1994)年については、本件事務所から、パートナーとしては、被告と小泉淑子弁護士がIPBAに参加し(これらのパートナーはそれぞれの参加費用を自己負担)、アソシエートとしては原告と藤本欣伸弁護士が参加したものと思われるが、事務所経費とされたのは(本件事務所が共通経費としてその経費を負担したのは)、藤本欣伸弁護士の参加費用のみである。
以上のとおり、原告の主張する「旅行」は、いずれも国際会議への参加をいうものと思われるのであって、「プライベートな旅行」などと評する余地は微塵とない。
なお、原告は本件事務所のパートナーとして、少なく見積もっても年間2000万円程度以上の収入はあったはずであり、被告との「収入格差は100倍以上」(そうであったとすれば、被告の収入は年間20億円以上ということになる)であったはずはなく、IPBAに毎年参加していたとしても、その参加費用が過重な負担であったはずもない。
(8)同8については、否認する。
(9)同9については、原告が事務所のクライアント先の人にプロポーズをされたことは知らず、その余は否認する。
被告は、原告から(誰かから)交際を申し込まれたとかプロポーズされたなどという話は聞いたことはなく、また、そもそも原告の主張する強迫は、被告の立場からするとそのような強迫をするとは考えられない不合理且つ不自然な内容である。
原告は、事務所のクライアントの誰から、いつ、交際を申し込まれ、又、プロポーズされたのかを明らかにされたい。
(10)同10については、事件の概要について、平成8(1996)年、クライアントであるA社が発行会社で、原告主張の日本の証券会社のスイス法人が引受証券会社となり、日本の証券会社が斡旋をして、社債発行、引受の発行会社側の代理人を本件事務所がつとめていたこと、最終的な契約条項が決定するまでの間にスイスフラン建転換社債の株式への転換条件が変更されたこと、及び、その変更によって最終的に原告が確認した条件との間で齟齬が生じたこと(整合が取れなかったこと)、そのため日本の証券会社側がその見落としについて、(見落としていた)原告と、(作業はしていなかったものの代理人として当該案件に名前が入っていた)被告との責任を追及していたことは認め、その余は争う。
原告は、日本の証券会社からの見落としの指摘に対して、当初は、ファックス書面で修正を支持した(見落としはしなかった)と弁解したが、日本の証券会社から「当該書面は真正のものであるとは到底考えられません」との回答(乙8)を受けて、そのような稚拙な弁解は当然撤回せざるをえなくなるとともに(なお、真に修正を支持したかどうかは措くとしても、確かに金融のプロであれば、修正が実際されたかを確認すべきであり、弁解としては通らない)、日本の証券会社の態度を硬化させた。
そして、もともと原告は金融を専門分野とし、当時、弁護士経験10年で本件事務所のパートナーをつとめていたのであって、案件の進行管理及びその作業内容に責任を持つべき立場であり、原告自身も、当時は、その認識のもと、(上記の弁解を撤回の後、)原告に過失があったことを前提として弁護士賠償責任保険の請求をし(乙9)、自らが本件で「失敗」を犯したことを認め、対応策について主導的に検討していた(乙10「私は〇〇(注:クライアント名)で失敗してから」)「〇〇(クライアント名)で先生に迷惑をかけた」「従って、JKM(注・原告)としては弁護士賠償保険の手続を進めてヘッジをかけるとともに、・・・話しを長引かせる事しかできないと思います」等)。
なお、当時の原告は、パートナーとして、誰からも労働を強制されたり労働管理される立場になかったものである。原告は、平成9(1997)年に1日19~20時間労働の日々が続いていたものと主張するが、平成9(1997)年の原告のタイムシートの平均の月間の時間は150時間程度であって(注・1ヶ月のうち20日程度稼働して稼働日1日あたり7・5時間程度をつけると、その程度になる)、本件事務所所属弁護士の平均時間より低かったのみならず、最低レベルにあった(乙7 MONTHLY TIME RECORDS抜粋(当該頁に記載されている弁護士のうち、原告の稼働時間が最も少ないものであることが分かる))。
(11)同11については、当時、原告がジュニア・パートナーとも言われる立場で、被告がシニア・パートナーとも言われる立場であったこと、富山で行われた会議には被告は出席しなかったこと(但し、これは、その日は被告の都合のつかない日であることが分かっていたにも関わらず、会議の日程調整を行なっていた原告が、あえてその日に会議を設定したためである)、平成10(1998)年夏ごろ、クレームの発端が原告主張の経緯であったこと、日本の証券会社が原告と被告の責任追及をしたこと、A社が日本の証券会社に対して調停を申立て、日本の証券会社が原告と被告を利害関係人としたこと、これらについて平成12(2000)年3月に利害関係人原告と被告が3500万円をA社に対して解決金名目(注・損害金名目ではない)で支払うという調停(注・和解ではない)が成立したこと、そのときに原告に代理人として丸山利明弁護士がいたこと、最終的に3500万円の半額である1750万円(但し後述するように、うち1000万円については保険金により補填したため実質負担は750万円)を負担したことは認めるが、その余は否認する。
同調停では、日本の証券会社はA社に対して4億3000万円近くの解決金を支払うとされたのであって、見落としをしたとして責任追及されている立場の弁護士が3500万円の負担となったことは穏当と評されるものと言えるし(そのうち相当額が弁護士賠償保険金で手当てされる見通しであればなおさらである)、調停時には、原告は、(本件事務所を下記(12)で述べる事情で辞めていたので、)原告自身の司法修習所時代の教官である丸山利明弁護士を代理人とし、被告は本件事務所所属の藤本欣伸弁護士を代理人として、それぞれ別の代理人をたてていた状況であるから、調停への出席が被告により妨害され、調停内容が原告の意に反するものであったかのような原告の主張は理解しがたい。
この点、原告は、調停成立の1週間程度前である平成12(2000)年3月25日(土曜日)に、被告代理人の藤本弁護士に対して、「3500万円払うのが落ち着きどころだと考え直しました」「火曜日には3500万円の線で妥結してください」「月曜にだいたい先が見えた場合には、私は調停期日を欠席します。丸山先生に一任していますし、もともと大事な会合と重なっていますので」「結局江尻先生にはご迷惑をかけてしまい、口惜しいです。」と書き送っており(乙10 メール)、原告に責任があったこと、原告自身が3500万円での妥結を望んでいたこと、原告自身が調停期日に欠席すると判断していたことが明らかである。なお、このとき、支払われる保険金を原告は1000万円と見込んでいたが(乙11の「一応1000万円出るという前提にします」「藤本先生には、少しでも多く保険をとっていただくよう、お願いします。」)、最終的には、その後の藤本弁護士の尽力により、保険金は同年6月19日に2000万円出ることになったので(乙12「保険金お支払のご案内」 なお、同案内に記載されている被害者はクレームの発端となった外債を購入した外国投資家である)、保険金補填後の最終的被告負担は、原告と被告とも750万円ずつであった。
(12)同12については、本件事務所が東京八重洲法律事務所と合併してあさひ法律事務所と改名したことは認めるが、その余は否認ないし争う。
まず、合併時期は、平成5(1993)年4月1日であり(乙1)、合併当時の弁護士数は、本件事務所(旧桝田江尻法律事務所)所属の弁護士が30名弱、東京八重洲法律事務所の弁護士が10名弱であった。
また、原告は、平成11(1999)年8月に本件事務所を退職したが、それは、原告が破産管財人となった複数の破産事件において、裁判所から支払われた管財人報酬について、報酬決定書を改ざんしたコピーを作り、それをもって、本件事務所に支払うべき事務所経費分(*売上のうち決められた一定割合を事務所経費として支払う必要があった)を誤魔化し、あるいは誤魔化そうとしたためである。当時、原告は、前述したとおり三宅省三弁護士の引立て及び口添えにより、その経験年数の割には規模の大きい破産事件を東京地方裁判所破産部から割当てられていたものであるが、破産事件の規模が大きいわりに原告が本件事務所に報告する破産管財人報酬額があまりに安すぎることに不信を抱いた本件事務所のマネージングパートナーたる弁護士ら(注・被告ではない)が調査したところ、調査対象となった複数の破産事件において、報酬額の誤魔化しがあったこと(最も規模の大きいものでは数千万円分の誤魔化しがあった)が発覚したのである。そこで、マネージングパートナーにおいて、調査の結果をもとに原告と話をしたところ、原告も不正の事実を認め、退職勧奨に応じたというのが真相である。このように、原告は、公文書変造や詐欺にも問議し得べき行為をしたにも関わらず、本件事務所及び被告は、原告に配慮してこの事実を可及的に伏せ穏便にことを運んできたものであるが、原告が本件事務所退職の経緯について、事実に反する主張をするのであれば、この点を証拠を持って明らかにせざるを得ないと考えている。
(13)同13については、否認ないし争う。
「逗子の物件」に関しては、被告が、平成15(2003)年前後に、妻とともに釣りに行ける別荘を、江ノ島、逗子、熱海あたりで数年にわたって探していたことがあるので(結局、購入しなかった)、その話を当時被告が原告にしたか、あるいは原告が他からの噂で聞いたものと思われる。
「文京区の土地」については、被告は、原告が親と同居することにしたという話を聞いた前後の頃であったが、何かのついでの機会に土地を見た記憶はあるが、それが「文京区の土地」であるかどうかは定かではない。
なお、原告の主張によれば、平成15(2003)年に「逗子の物件」の話が出たものの、その後何の話も出なくなったので、困惑しながらも、「文京区の土地」を購入することとなったとのことであるが、原告が文京区の土地を購入したのは平成14(2002)年7月5日のことであるので(乙13の1、2 登記情報)、原告の主張する時系列(前後関係)は矛盾している。また、被告は、同土地上に建設された建物がどのようなものであるかは一切知らないが、建築当初から建物に付されていたと思われる表札には「森」としか表示されていないことから明らかであるように(乙13の4 グーグルマップ)、同建物は原告がその判断で自ら(と両親のみ)の居所として建築したものと思われる。
(14)同14については、原告が「池之端のマンション」「用賀のマンション」「神保町のマンション」を保有し、それらに関して原告主張とおりの経済的負担をしたこと、被告が原告に対して送金(原告主張によれば61万2000円)をしたことは特に争わないが、その余は争う。
被告は原告に対して、原告保有のマンションの家賃や管理費を支払う約束をしたことはない。また、被告が原告にした送金について、被告に具体的な記憶はないが、原告は、本件事務所を上記事情で退職した後、入所した事務所を何度か変え、その度に被告に相談があったため、被告は新たな事務所を紹介したり、また仕事も決して順調ではないだろうと思われたため案件を紹介ないし依頼したり、時には被告が紹介した案件で原告が弁護士費用を取りっぱぐれた場合には多少の埋め合わせをしたりして、原告に気を配ってきた。そのような配慮の一環として、61万2000円の送金をした可能性がある。
(15)同15「2008年末からの被告の裏切りー慰謝料と加算事由」については、2008年末頃には、原告が、被告に原告との結婚の意思がないと理解するようになってきて、その後疎遠な状況になっていき、原告が被告に対して平成25(2013)年6月12日に調停を申立て、それが不調に終わったという、原告と被告との関係の終了を述べるものとして、特に争わない。
3(1)同3、1の1)ないし4)については、4)を除き、原告が地震でその主張する名目・金額の負担を負うことについては特に争うものではないが、被告に負担義務があることについては争う。4)については、事実及び法律上の根拠にかける本訴提起追行費用として弁護士費用639万円は課題と思われる。
(2)同2については、争う。
なお、「⑧1億8000万円のローンを今も負わされている」については、乙13の1ないし3(登記情報)を見る限り、原告保有の文京区物件の抵当権が抹消されていることに照らして措信しがたい。原告は、その主張するローンの詳細及び現時点での残高を明らかにされたい。
第2 被告の主張
1 法的保護に値する結婚約束の不存在
被告と原告との間には、結婚の約束となる会話はなかったものであるが、会話以外にも一般的に結婚の約束をしたことを推認させる根拠(指輪の交換、親戚への紹介その他)もまったく存在していない。
そればかりか、被告が当時婚姻していたことからすると、仮に結婚の約束と思われる会話があったとしても、それに対して軽々と結婚約束がなされたと信頼するとは考えがたく(当時、原告は少なくとも弁護士経験を4年程度積んで35歳にはなっていたことからすれば尚更である)、また、仮に信頼をしたのであるとしても、そのような信頼は法的保護に値しない。
2 公序良俗違反
仮に原告と被告との間で結婚の約束が存在したとすれば、それは被告の妻に対する不法行為(半倫理的で社会的相当性を欠く行為)であるから、公序良俗違反(民法90条)により無効である。3 不法原因給付
仮に原告が被告との結婚の約束を前提として何らかの支出をしたとしても、結婚の約束自体被告の妻に対する不法行為(反倫理的で社会的相当性を欠く行為)となるのであるから、その支出について原告に対する分担請求権、あるいは原告に対する損害賠償請求権は、法の保護に値するものではなく、民法708条の類推適用によって、原告の請求は許されない、
4 消滅時効・除斥期間(民法724条)
仮に原告の被告に対する何らかの請求権があるとしても、それが不法行為に基づくものであるならば3年で時効消滅するので(民法724条)、被告は原告に対して消滅時効を援用する。したがって、被告は、原告が本訴を提起した時(訴状の日付によれば平成26(2014)年4月15日)から3年以上前の事実を基礎として損害賠償義務を負うものではなく、またこれらが慰謝料算定の基礎とされるべきではない(3年以上前の行為については不法行為を構成しない)。
さらに、不法行為から20年を経過すると除斥期間にかかるため(民法724条)、原告は被告に対して、原告が本訴を提起した時から20年以上前(平成6(1994)年以前)の行為について不法行為による損害賠償請求権を行使できない。
5 和解
原告は被告に対し、平成24(2012)年7月に、被告との関係「終了」にあたっての「解決」として、金5000万円を貸付金名目で要求したため(乙14)、被告が代理人を通じて「今後、一切、経済的支援の要請や要求をしないこと」を条件に一定の経済的視点をする意思を示したところ(154)、原告は、1700万円を「和解金として」提示してくれればその場で合意するとし(乙16 但し原告からのメールを被告が被告代理人へ転送したもの)、結局、同月26日に被告から1700万円を「不法行為による損害賠償(慰謝料)として」受領した(乙17・18)。
この経緯からすれば、原告と被告は、平成24(2012)年7月26日、被告から原告に対する1700万円を支払うことによって、両者間の一切の関係を清算しその後原告は被告に対して何ら請求をしないという和解契約が成立したものである。従って、原告が本訴で主張する請求権は(仮にあったとしても)和解条項により消滅し、原告の被告に対する請求は許されない。
6 結論
以上のとおり、原告の請求はおよそ認められる余地はなく、本訴は、事実上及び法律上の根拠なく提起されたものと言わざるを得ない。本訴の提起は、それ自体、原告の被告に対する違法行為を構成する可能性があるほか、訴状では、被告について、「徹底した自己中心、保身の人」「小心者」「吝嗇さ」「非常識」「被告にとって、コントロールが全てである。他人を信用できないので、真の意味での愛情を持てないのが被告である。」などと徒に侮辱的表現を用いるのであって(16頁、17頁)、弁護士職務基本規定(第6条「弁護士は、名誉を重んじ、信用を意思するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める」、第70条「弁護士は、他の弁護士・・・との関係において相互に名誉と信義を重んじる」)上も問題なしとはしない。
第3 求釈明
1 原告が主張する「婚約」について、原告は、被告による申し込みが平成3(1991)年12月にあったと主張するようであるが、原告による承諾がいつであるかを明らかにされたい。原告の承諾の時期を明らかにし、婚約がいつ成立したのか明らかにされたい。
2 原告が主張する婚約「不履行」について、被告が不履行(婚約破棄)をした時期を特定されたい。
3 原告は、訴状第3、1の1)ないし3)で被告が原告に対して支払義務を負うと主張するそれぞれの「損害」について、訴状第2のタイトル中に「不法行為(民法709条)」とともに「債務不履行(民法第415条)」が挙げられていることに照らして、それぞれの損害と「債務不履行」の関係を明らかにされたい。また、これらの「損害」について、「債務不履行」のほかに、原告と被告との支払合意を直接の請求根拠とするのかどうか、請求根拠とするのであれば、当該合意の時期及びその内容を明らかにされたい。
4 原告は、訴状第3、2に記載する「慰謝料」について、訴状第2のタイトル中に「不法行為(民法第709条)」と「債務不履行(民法415条)」の双方が挙げられていることに照らして、いずれを請求根拠とするのか、あるいは双方を請求根拠とするのか明らかにされたい。また、債務不履行についてもその請求根拠とするのであれば、なぜ債務不履行によって慰謝料が発生するのかを説明されたい。
5 平成24(2012)年7月に、被告が原告に交付した1700万円の支払がどのような合意に基づくものであるのかその性質を明らかにされたい。
これが和解金ではなく、あるいは仮に和解金であるとしてもその後の原告の被告に対する本訴請求が許されるとすれば、被告は原告に対して(和解の前提についての錯誤その他の事由により)、反訴提起等により1700万円の返還請求をする所存である。
以上